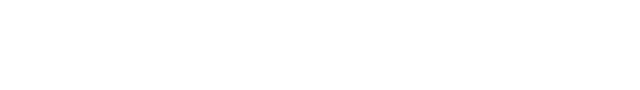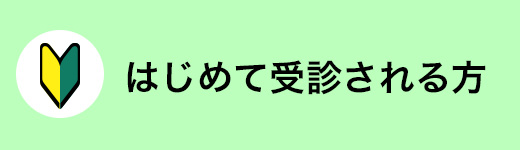眠れない夜がつづくあなたへー精神科専門医が不眠症の治療法を解説します
こんにちは。
江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック 院長の三木敏功(精神科専門医 産業医)です。
「布団に入ってもなかなか眠れない」
「夜中に何度も目が覚める」
「朝早く目が覚めて、そのあと眠れなくなる」
そんな“眠れない夜”を、あなたはどれくらい続けていますか?
睡眠は、心と身体を整えるための大切な回復の時間です。
それなのに、毎晩のように寝つけなかったり、眠っても疲れがとれなかったりする――このような状態が続くと、日中のパフォーマンスは落ち、気分も沈み、心の健康にも影響を及ぼします。
今回は、「不眠症ってなに?」「薬に頼って大丈夫?」「どうすれば眠れるの?」といった疑問に、脳科学・薬物療法の視点から、やさしく丁寧にお答えします。
【目次】
1. 不眠症とは? ― 睡眠不足だけではない“こころの病気”
2. 脳の“誤作動”が不眠の原因になる
3. 「眠らなきゃ」と思うほど眠れない理由
4. 睡眠薬は“脳のスイッチを助けるツール”
5. 日常でできる「眠りの習慣づくり」
6,不眠が脳と身体に与える悪影響
7,最後に ―「眠れないこと」は、あなたのせいではありません
8,.参考文献・出典
1. 不眠症とは? ― 睡眠不足だけではない“こころの病気”
不眠症とは、「十分な時間寝ようとしているのに眠れない」状態が、週3回以上・1か月以上続き、日常生活に支障をきたしていることをいいます。
症状は大きく分けて4つあります:
- 入眠困難:寝つきが悪く、30分〜1時間以上かかる
- 中途覚醒:夜中に何度も目が覚める
- 早朝覚醒:予定よりも早く目覚め、再入眠できない
- 熟眠障害:眠った感覚がなく、朝から疲労感が残る
日本では、成人の約20%が慢性的な不眠に悩んでいるとされており、年齢を重ねるほど頻度は高くなります。
また、うつ病・不安障害・ADHDなどの精神疾患のサインとして不眠が現れることも非常に多いのです。
2. 脳の“誤作動”が不眠の原因になる
睡眠にとって重要なのは、自律神経のバランスです。
- 交感神経(活動・緊張のモード)
- 副交感神経(休息・回復のモード)
夜になると、副交感神経が働き身体がリラックスすることで、自然な眠りに入るはずですが、ストレスや情報過多によって交感神経が優位なままになると、脳は「過覚醒・興奮モード」のまま、眠りのスイッチが入りにくくなります。
これは脳の「視床下部」や「脳幹」など睡眠調整を行う部位がうまく働かないことが関係しています。
つまり、不眠は“気の持ちよう”ではなく、脳の機能の一部が誤作動を起こしている状態とも言えるのです。
3. 「眠らなきゃ」と思うほど眠れない理由
「眠らなきゃいけない」「明日がつらくなる」――
そう思えば思うほど、かえって眠れなくなる…そんな経験はありませんか?
これは「入眠恐怖」とも呼ばれます。
眠れないこと自体がストレスになり、脳がさらに興奮状態になって眠りを妨げるという悪循環です。
睡眠は“努力して得るもの”ではなく、“力を抜いた先にやってくるもの”。
「眠れない自分を責めないこと」が何よりも大切です。
4. 睡眠薬は“脳のスイッチを助けるツール”
「睡眠薬=クセになる」というイメージをお持ちの方は少なくありません。
しかし現在の睡眠薬は、安全性や依存性への配慮がなされた薬が多く登場しており、正しく使えば怖いものではありません。
主な種類としては:
- ベンゾジアゼピン系・非ベンゾ系:脳の緊張をやわらげて眠りに入りやすくする
- メラトニン受容体作動薬:体内時計に作用し自然な眠気を導く
- オレキシン受容体拮抗薬:脳の「覚醒スイッチ」を抑える
- 抗うつ薬・抗不安薬:不安や気分の波を整えて間接的に眠りを支援
副作用や依存のリスクを最小限に抑えながら、必要な分だけ“脳のスイッチをサポート”する薬を処方しています。
必要最低限の量で、一定期間の服用で完治を目指していきます。
5. 日常でできる「眠りの習慣づくり」
薬物療法と並んで重要なのが、生活習慣の見直しです。以下の習慣が眠りやすい体と脳をつくります。
- 就寝1時間前からスマホやPCを控える
- 寝室を「眠る場所だけ」に限定する
- 眠れないときは布団を出てリラックスできる行動を
- 朝は決まった時間に起床し、朝日を浴びる
- 軽い運動(散歩・ストレッチなど)を日中に取り入れる
- 寝る前のカフェインやアルコールを控える
また、「不眠に特化した認知行動療法」も有効な心理療法です。
「眠らなきゃ」と思う気持ちそのものを調整する心のアプローチで、できるだけ薬に頼らず眠れる状態を目指します。
6. 不眠が脳と身体に与える悪影響
「たかが寝不足」と思われがちな不眠ですが、脳や身体には想像以上に深刻な影響を与えることがわかっています。
◆脳への影響
-
集中力・記憶力の低下
睡眠中、脳は「情報の整理」や「記憶の定着」を行っています。眠れない日が続くと、物忘れが増えたり、仕事や勉強でミスが増えたりすることがあります。 -
感情のコントロールが乱れる
不眠は、感情を調整する前頭葉の働きを低下させ、イライラや不安感、落ち込みを強くする要因となります。
長期間続くと、うつ病や不安障害のリスクも高まります。 -
脳の老化が加速する可能性も
最新の研究では、慢性的な不眠がアルツハイマー病などの認知症のリスク因子になる可能性が指摘されています。睡眠不足は脳内の老廃物の排出を妨げるためです。
◆ 身体への影響
-
免疫力の低下
睡眠中には、免疫細胞の働きが活発になります。不眠が続くと風邪をひきやすくなったり、病気の治りが遅くなることも。 -
高血圧や糖尿病のリスク上昇
不眠によって自律神経のバランスが崩れ、血圧や血糖値の調節機能が乱れることが知られています。 -
肥満の原因になることも
睡眠不足は、食欲を調整するホルモン(レプチンとグレリン)のバランスを乱し、過食や体重増加につながる可能性もあります。
眠りは、脳と身体の修復作業の時間です。
たとえ「なんとか生活できている」と感じていても、不眠を放置することで、少しずつ心身にダメージが蓄積されていきます。
だからこそ、「最近ずっと眠れないな」と思ったら、それは身体からのSOSサインかもしれません。
早めに受診し、一緒に“眠れる自分”を取り戻していきましょう。
7. 最後に ―「眠れないこと」は、あなたのせいではありません
不眠症は、決してあなたの“心が弱い”からではありません。
脳の仕組みやこころのストレスによって引き起こされる、“治療可能な病気”です。
そして、不眠が続くことで、うつ病や不安障害、心身症などにつながることもあります。
だからこそ、眠れないことをひとりで抱え込まず、精神科専門医に早めのご相談をおすすめします。
薬物療法・生活習慣の改善・心理的アプローチを組み合わせて、あなたに合った眠りの回復プランを一緒に考えていきます。
8,【参考文献・出典】
- 日本睡眠学会『不眠症診療ガイドライン』
https://www.jssr.jp/data/guideline.html 定期的に読んでおります。 - 厚生労働省 e-ヘルスネット「不眠症」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-038.html
※不眠の原因や対応について、国の健康情報サイトによるわかりやすい解説。多くの方に参考になる情報です。 - American Academy of Sleep Medicine(AASM)
Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Chronic Insomnia in Adults
https://aasm.org/clinical-resources/practice-standards/practice-guidelines/
※慢性不眠症に対する国際的な診療ガイドラインです。精神科医必読の論文です。 - NICE guideline [NG215]: Insomnia: diagnosis and management
https://www.nice.org.uk/guidance/ng215
※英国の医療評価機関による不眠症の診断と治療に関するガイドラインです。勉強になる論文です。