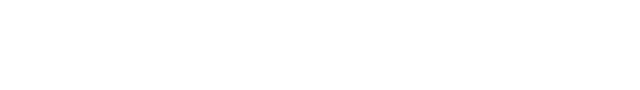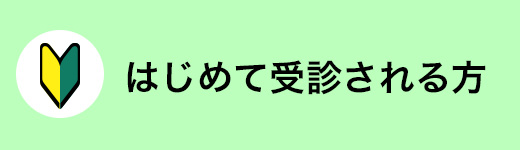【保護者の皆様へ】子どもの精神科訪問看護の役割と活用法 〜「頼りすぎると学校に行けなくなる?」その疑問に児童精神科医が解説します〜
こんにちは。
江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック院長の三木敏功(児童精神科医 子どものこころ専門医)です。
「訪問看護」と聞くと、大人の患者さんや高齢者の方に使われるサービスというイメージが強いかもしれません。しかし、子どもや思春期の子たちにとってもとても有効な支援ツールであることをご存じでしょうか?
今回は、児童や思春期の子どもに対する精神科訪問看護について、保護者の皆さまがよく抱える疑問や不安にお答えしながらお伝えします。
【目次】
-
精神科訪問看護とは?
-
「訪問看護に頼ると学校に行けなくなる?」という誤解
-
訪問看護で実際に行うこと
-
費用はどのくらい?
-
訪問看護の頻度は?
-
「うちの子に必要?」の判断
-
「他人が家に入ってくるのが抵抗ある…」という気持ちについて
-
保護者の皆さまへのメッセージ
-
最後に
- おすすめの書籍
1,精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護とは、精神的な不調を抱える方のご自宅や学校、施設などに看護師や作業療法士などの専門職が訪問し、治療や生活支援を行うサービスです。
大人の場合は「再発予防」「服薬管理」「社会復帰支援」などが主ですが、児童の場合には、
- 不安、心配の軽減
- 学校や社会生活へのステップアップ支援
- ご家族のサポート
- 特性の理解を促す なども目的となります。
2,「訪問看護に頼ると学校に行けなくなる?」という誤解
よく「訪問看護を入れたら、家にずっといることが習慣化してしまうのでは?」という心配を耳にします。
実際には、その逆です。
訪問看護では「外に出るための準備」や「少しずつ自立を促す練習」をするケースがほとんどです。
例えば、
-
朝決まった時間に起きる練習を一緒にする
-
学校までの道を一緒に歩く練習をする
-
学校内で過ごすときに使える「心のコーピング方法」を考える
といった「学校に戻るためのステップ」を看護師や専門職が一緒に取り組みます。
そのため、むしろ 登校や社会復帰を後押しする役割 と考えていただければと思います。
3,訪問看護で実際に行うこと
訪問看護は、医師の指示書(訪問看護指示書)をもとに、子ども一人ひとりの状態に合わせた内容を行います。具体的には以下のような支援があります。
-
気持ちの整理と共有
学校での出来事や家庭での困りごとを一緒に整理し、「今何が辛いのか」を一緒に考えます。 -
生活リズムの支援
昼夜逆転の修正、決まった時間に起きる・食べるなどのリズムづくり。 -
対人関係のトレーニング
人とのやり取りの練習や、自分の気持ちを上手に伝える練習。 -
保護者への助言
お子さんとの接し方、声かけの仕方、学校との調整方法など。 -
薬の管理
服薬状況の確認や副作用のチェックなど。
「訪問」といっても、いきなり何か大きなことをするわけではなく、最初は「顔を合わせる」「話す」から始めることが多いです。
4、費用はどのくらい?
訪問看護は医療保険と公費負担制度が使えます。
児童の場合、多くの地域で「こども医療費助成制度」や「自立支援医療(精神通院医療)」を利用できます。
例えば、東京都内の多くの自治体では、医療費助成により自己負担が無料または月数百円程度になるケースもあります。
ただし、自治体やご家庭の保険状況によって異なるので、詳しくは訪問看護ステーションにご確認ください。
5,訪問看護の頻度は?
一般的には 週1回程度 からスタートしますが、必要に応じて増える場合もあります。
お子さんの調子や保護者の希望、学校復帰の進捗状況に応じて柔軟に調整できます。
また、状態が安定してきたら徐々に回数を減らし、最終的には訪問が不要になることを目指します。
6,「うちの子に必要?」の判断
「訪問看護ってうちの子にも必要?」と迷われる保護者の方はとても多いです。
以下のような場合は、一度検討してみてもよいかもしれません。
- 学校や外出への強い不安があり、朝になると体調不良を訴える
- 昼夜逆転が続き、家族だけでは立て直せない
- 友だちとの関係がうまくいかず、対人不安が強い
- 突然のパニックや不安発作が多い
- 保護者が一人での対応に限界を感じている
「訪問看護はハードルが高い」と思われがちですが、実際には「一歩ずつ外に向かうための伴走者」としての役割が大きいです。
7,「他人が家に入ってくるのが抵抗ある…」という気持ちについて
訪問看護のご相談を受けるとき、保護者の方からよく聞くお声の一つが
「正直、家に他人が入るのは抵抗がある」
というお気持ちです。
これはとても自然で、当たり前の感覚です。
初めて訪問にうかがうときにはとても慎重に配慮してもらえます。
例えば、
-
お子さんやご家族の了承をきちんと取ったうえで訪問を開始する
-
初回は短時間に設定し、無理なく慣れていけるようにする
-
必要であれば、家の中ではなく玄関先など外でお話をする
といった柔軟な対応をしてくれるところが増えています。
特に児童、思春期年齢の場合、「家に入って話すのが難しい」「部屋に知らない人が入るのは怖い」ということがあります。
その場合には、「まずは会うだけ」など、段階的に進めることができます。
「他人が家に入るのは怖い」「何を見られるのか不安」というお気持ちは、とても大事な気持ちです。
むしろそのように思えること自体、お子さんやご家庭を大切に思っている証拠です。
訪問看護は「一歩ずつ」「一緒に考えながら」進める支援です。
どんな小さな不安でも、まずは主治医や看護師に気持ちを打ち明けてみてください。
🌱 架空事例① ― 玄関先からの一歩
小学校5年生のAくんは、ずっと家に引きこもっていて、知らない人と話すことがとても怖い状態でした。
初めての訪問看護のときは、看護師が玄関先で5分だけ「こんにちは」と挨拶するところからスタートしました。
2回目、3回目は玄関先でちょっとしたカードゲームをするようになり、徐々に「次は一緒に外を歩いてみようか」と提案。
4か月ほど経つと、近所の公園まで一緒に行けるようになり、最終的には学校の先生と面談に行くときも、一人で登校できるようになりました
Aくんのお母さんは、「最初は家に人を入れるなんて絶対に無理だと思ったけど、段階的に進めてくれたので、本人も私も慣れていけました」と話しています。
🌱架空事例② ― 保護者と一緒に始める
高校生のCくんの場合は、「1人では絶対に無理」と強い拒否がありました。
そこで、最初の3回は必ずお母さんが横に座って、一緒に話すスタイルにしました。
回を重ねるごとに「今日はお母さん、ちょっと別の部屋にいていいよ」と自分から言えるようになり、自信を取り戻していきました。
8,保護者の皆さまへのメッセージ
子どもが外に出られない、学校に行けないという状態は、決して甘えや怠けではありません。
そこには強い不安、自己否定感、過去の失敗体験など、さまざまな背景が隠れています。
保護者の皆さまも、孤独感や無力感を抱えておられるかもしれません。
「もう頑張り方がわからない」と感じたとき、精神科訪問看護という新たな選択肢を思い出してください。
お子さんとご家族を「待つ」だけではなく、「一緒に進む」ための支援が、訪問看護にはあります。
9,最後に
当院では、地域の訪問看護ステーションと密に連携しながら、お子さん一人ひとりの状態やペースに合わせたサポートを大切にしています。
「どこから相談していいか分からない」
「まだ訪問看護を使う段階ではないかも」
そんな風に迷われる保護者の方も多いです。
でも、まずは「話を聞いてみるだけ」でも大丈夫です。
訪問看護は、無理に決めるものではなく、お子さんと保護者の気持ちを尊重しながら、一緒に進め方を考える支援です。
お子さんの心の回復や生活リズムづくり、学校復帰のきっかけ作りなど、一歩一歩を支えるお手伝いができます。
保護者の方が「一人で抱えない」ための味方にもなれます。
「これから先、本当に学校に戻れるのだろうか」
「どうやって一歩を踏み出せばいいのか分からない」
そんなときこそ、私たちにご相談ください。
お子さんが自分らしく生きる力を取り戻し、未来の可能性を広げていけるよう、一緒に考え、一緒に支え続ける存在でありたいと思っています
10、おすすめ書籍
-
厚生労働省「精神科訪問看護の手引き」(最新版)→とても参考になります。支援者向けの内容です
-
日本精神科看護協会『精神科訪問看護ガイドブック 改訂版』(中央法規出版)→支援者向けの内容です。訪問看護支援について示唆に富む内容となっております。
-
日本児童青年精神医学会『子どものこころの診療ガイドライン』
-
河合隼雄著『子どもの心をひらく』(岩波新書)→歴史的臨床的名著であります。何度も何度も読んでおります。
-
宮田俊男著『子どもと家族のための精神科治療ガイド』(診断と治療社)→家族支援についてこの本から多くのことを学びました。