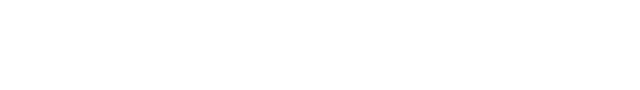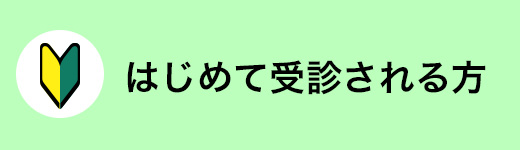「我が子が発達障害かもしれない」と思ったときに
こんにちは。江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック、院長の三木敏功(児童精神科医、子どものこころ専門医)です。
今回は、「我が子に発達障害かどうか調べてほしい」「発達に特徴があるのでは」といったご相談について、お話ししたいと思います。
発達障害は「特別なこと」ではありません
近年、「発達障害」という言葉を耳にする機会が増えています。
発達障害とは、脳の発達の特性により、行動や感覚、コミュニケーションに偏りが見られ、生活の中で困難を感じやすい状態のことです。
代表的なものに、
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などがありますが、一人ひとりの状態は異なり、はっきりと線を引けるものではありません。
よくあるご相談の背景
当院にも、「我が子は発達障害ではないかと心配です」「検査で調べてほしい」というご相談が多く寄せられています。
たとえば、
- 集団行動が苦手で友達とうまく関われない
- 忘れ物やミスが多く、集中力が続かない
- 急な予定変更にパニックになる
- 音やにおい、手触りに過敏に反応する
- 空気が読めない、誤解されやすい
といった特徴から、「性格の問題ではなく、発達の特性かもしれない」と受診につながることがあります。
検査は「最初にすぐやる」ものではありません
ここでお伝えしたい大切なことがあります。
当院では、治療の初期段階からすぐに複雑な心理検査を行うことはしていません。
特にお子さんの場合、初めての場所や人に緊張しやすく、気持ちを言葉にできないことも多いため、まずはクリニックに慣れて、安心して過ごせるようになることを大切にしています。
そのうえで、必要と判断された場合には、発達検査や知能検査を行います。
これらの検査は、診断をつけるためだけでなく、「その子がより過ごしやすくなる方法を一緒に考える」ための手がかりでもあります。
診断よりも「理解」と「支援」が大切です
発達障害は「病気」ではなく、「特性」です。
苦手なことがある一方で、得意なことや個性豊かな一面を持っている子どもたちがたくさんいます。
そのため、診断名にとらわれるよりも、「どんなサポートがあれば、その子らしく生きやすくなるか」を考えることが大切です。
当院の治療の特徴
当院では、発達障害そのものよりも、不登校、抑うつ、パニック、癇癪などの二次的な困りごとへの対応を重視しています。低下した自尊心を回復させることを大切にし、薬物療法などをきっかけに、前向きな治療につなげるサポートを行っています。