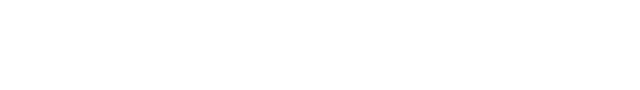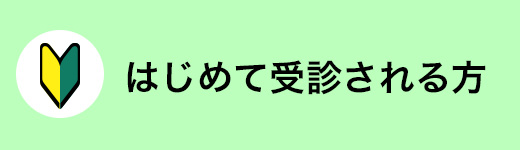【福祉・支援者の皆様へ】支援が必要な保護者が語る「ファンタジー(妄想)」をどう理解し、どう支えるか ─ 児童精神科医が解説
こんにちは。
江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック 院長の三木敏功(児童精神科医 子どものこころ専門医))です。
私はこれまで、児童相談所、児童養護施設、医療機関などさまざまな現場で、子どもと保護者の支援に関わってきました。
その中で、支援が必要な保護者が抱える「ファンタジー(妄想)」に触れる機会は少なくありません。
支援者として、この「語られる物語・ファンタジー」にどう向き合えばよいか悩む方はとても多いと思います。
このブログでは、福祉司さんや支援者の方々に向けて、実践的な視点と心がまえをお伝えしたいと思います。
【目次】
1. 「ファンタジー」と「精神病性の妄想」は異なる
-
ファンタジーとは?
-
精神病性妄想の特徴
-
医療的対応の違い
2. なぜ保護者はファンタジーを語るのか?
-
ストレスからの逃避
-
愛着欲求と承認欲求の表現
-
コミュニケーションの道具として
-
言葉にできない感情の代弁
3. 「共感」と「同情」の違い
-
なぜ同情は危険なのか
-
ファンタジーが強化されるリスク
-
現場での具体的声かけ例
4. 「ないがしろにしない」というバランス
-
傾聴のポイント
-
ファンタジーを放置してはいけない理由
5. 支援が必要な保護者の特徴的な課題
-
コミュニケーションの抽象度
-
繰り返し説明の重要性
-
書面や視覚資料の活用
6. 具体的な危険性がある場合の対応
-
緊急性のあるケース
-
多職種チームによる安全確保
7. 現場で使える具体的対応例
-
ファンタジーを「橋」とする活用法
-
支援計画への活用と共有
8. 支援者が大切にしたい「線引き」とバランス感覚
-
現実重視の視点
-
「いい人」になりすぎない
-
感情管理と記録の重要性
9. 子どもへの影響とリスク
-
現実との接点喪失の危険性
-
過剰適応や役割混乱
-
二次障害と社会参加への影響
-
子どもに必要な「現実を生きる力」
10. 最後に ─ 支援者の皆さんへ
-
支援者の役割と応援メッセージ
-
相談とチーム支援の大切さ
11. 参考文献・資料
1,「ファンタジー」と「精神病性の妄想」は異なる
まず大前提として、支援が必要な保護者が語るファンタジーと、統合失調症などの精神病性妄想は別物です。
✔️ ファンタジーとは
-
日常の辛さやストレスから自分を守るための空想世界
-
自分の価値や子どもの特別さを守りたい願いの表現
-
現実検討能力(現実と空想を見分ける力)はある程度保たれている
✔️ 精神病性の妄想とは
-
統合失調症などに見られる「事実と完全に切り離された確信」
-
他者が論理的に説得しても揺らがない
-
被害妄想、関係妄想、宗教妄想など、内容が特定される
精神病性の妄想には、現実検討能力の著しい低下が伴い、論理的に説明できない確信や被害感覚が強く現れます。抗精神病薬の服用により妄想の症状が改善が期待できます。
一方、支援が必要な保護者が語るファンタジーは、あくまで「現実から逃避するための物語」であり、ストレス対処の一環であることが多いです。
とても大事なポイントです。
2, どうしてファンタジーを語るのか?
ファンタジーの背景には、本人が抱えるさまざまな思いが隠されています。
✔️ ストレスからの逃避
現実が過酷すぎるとき、人は空想の世界に身を置いて自分を守ろうとします。
これは一種の心の防衛であり、本人にとっては「生き抜くための方法」なのです。
✔️ 愛着欲求の表出
「誰かに愛されたい」「認められたい」という強い欲求が、物語を通じて表現されることがあります。
特に支援が必要な保護者の場合、対人関係のつまずきが多く、周囲の反応を過剰に気にしてしまう傾向があります。
✔️ コミュニケーションの道具
ファンタジーは、言葉だけでは伝えきれない思いや願いを届ける手段でもあります。
「子どもは宇宙から来た特別な存在」と話す保護者がいた場合、それは「子どもを特別な存在として守りたい」という気持ちの裏返しとも受け取れます。
✔️ 言葉にできない感情を代弁する手段
「つらい」「助けて」が直接言えない代わりに、空想的なストーリーに託して伝えることもあります。
3, 同情しすぎるとファンタジーが強化される理由
支援者として一番大事なのは、「共感」と「同調」を混同しないことです。
✔️ 共感・傾聴は必要、同情は危険
-
共感・傾聴:相手の気持ちを理解し、受け止める
-
同情:相手の世界観を肯定して一緒にその世界に入ってしまう
支援が必要な保護者の場合、支援者が深く「そうだよね、それは本当だよね」と同情してしまうと、物語が現実世界の中でより強く固定化され、行動や養育判断にも影響が出ます。
例えば、
「子どもは特別な使命を持つ天使だから、学校に行かせなくていい」といった物語・ファンタジーが強化されると、実際の子どもの発達や社会生活に大きな支障が出ることがあります。
4,「同情」ではなく「共感・傾聴+現実志向」を
支援者として重要なのは「寄り添いながら、現実に戻すための足場をつくる」ことです。
✔️ なぜ「同情」はNG?
同情すると、支援者自身が「助けなきゃ」「この人を全て理解しなきゃ」という責任感に飲み込まれます。
結果として、支援者自身が妄想に飲み込まれ、自身の感情コントロールが難しくなります。安定した支援関係が構築できず、支援関係が破綻する可能性が高まります。
✔️実際の現場での声かけ例
-
「それほどお母さんにとって大切な話なんですね」
-
「そのお話には、お母さんの強い願いが詰まっている気がします」
-
「一緒にお子さんのこれからの現実の生活も考えてみませんか?」
これらは、ファンタジーを完全に否定せず、同時に現実への視点を少しずつ入れるテクニックです。
5, 共感・傾聴は大切、でも「ないがしろにしない」というバランス
ファンタジーを一方的に否定したり、無視したりすると、支援が必要な保護者は「理解してくれない」「敵だ」と感じ、支援関係が崩れてしまいます。
✔️ 傾聴のポイント
-
内容の「事実性」を議論しない
-
お母様の「気持ち」に注目する
-
「なぜそう思ったのか」を丁寧に問いかける
たとえば、
「お母さんがそう思うのは、何か不安があるからかもしれませんね。」
「そのお話を聞いていると、お母さんがすごく頑張っているのが伝わります。」
これらの声かけは、ファンタジーを肯定しているわけではなく、気持ちに寄り添いつつ、現実への足場を保つ方法です。
✔️ファンタジーを放置してはいけない理由
ファンタジーは、一見無害に見えるかもしれませんが、次のようなリスクを伴います。
-
子どもが医療・教育・福祉の支援を受けられなくなる
-
子どもの現実適応が妨げられ、二次障害(不登校、引きこもり、対人恐怖など)が発生
保護者自身がさらに孤立し、虐待リスクが上昇する可能性があります。
6,支援が必要な保護者の特徴的な課題と支援
✔️ コミュニケーションの抽象度が低い
抽象的な説明が難しく、具体的に伝えることが大切です。
「頑張ろうね」ではなく、「今日の面談では〇〇について話します」と具体的に設定します。
✔️ 繰り返し説明が必要
一度伝えただけでは理解が難しい場合が多く、短くわかりやすい表現で、何度でも説明する覚悟が必要です。
✔️ 書面の活用
視覚情報の方が理解しやすい場合が多く、説明内容を図やイラスト、簡単なメモにすることが有効です。
7, 具体的な危険性がある場合は
語られる内容が、養育の放棄や虐待につながる可能性がある場合は、即座にアセスメントと介入が必要です。
-
子どもを「全知全能の神の使い」と信じこみ、身体的・精神的に治療が必要にも関わらず、保護者が医学的治療を拒否する
-
「悪いエネルギーを払う」と称して子どもに身体的虐待を行う
こういった場合は、多職種チームと協力し、安全確保を最優先します。
8, 現場で使える具体的対応例
✔️ファンタジーの話を「橋」とする
ファンタジーは、支援者と保護者をつなぐ「橋」と考えるとよいでしょう。
内容を全面的に受け入れるのではなく、話題にしつつも現実の課題に少しずつ戻す工夫をします。
例:「そのお話はとても特別ですね。ただ、現実の中でお子さんが学校でどう過ごしているかも一緒に考えてみたいです。」
✔️支援計画の一貫として使う
「ファンタジー・物語」を一つの材料と捉え、保護者の希望や恐れを共有しながら支援計画を立てます。
支援チームで共有するときも「ファンタジーの内容」よりも「背後にある不安」を重点的に伝えます。
9,気をつけたい「線引き」「バランス感覚」
✔️ 目の前の現実を重視
物語・ファンタジーの内容にのめり込まず、子どもと保護者が直面する「現実の問題」に視点を戻す。
✔️ 「いい人」になりすぎない
支援が必要な保護者に好かれようとしすぎると、適切な指摘や介入ができなくなります。
✔️ 支援者自身の感情管理
ファンタジーの中には支援者の共感性を試す「引き込み」要素があります。
支援者自身の感情の揺れを自覚し、冷静さを保つことが不可欠です。
-
聴くが、のめり込まない
-
否定せず、事実確認を別途行う
-
必ず記録に残す(後の安全管理、法的根拠の確保)
福祉の皆様さんは、とても責任の重い立場です。
「一緒にいてあげたい」という気持ちが強い方ほど、ファンタジーの世界に引き込まれやすくなります。
そこで一度立ち止まり、「子どもの安全とお母様の福祉を守る」という大原則を忘れないことが大切です。
10, 子どもへの影響とリスク
✔️ファンタジー・物語が強化されると、子どもは 現実との接点を失い、自分自身の存在価値や役割を見失う 危険性
特に幼少期や思春期は、社会性や自我を育むとても大切な時期です。
この時期に「現実世界での小さな成功体験」を積むことが、将来の 自己肯定感 や 社会参加 に直結します。
しかし、支援が必要なお母様が語るファンタジーに巻き込まれすぎると、子どもは「現実をどう生きるか」ではなく、「物語の中での役割」 を優先するようになります。
たとえば、
-
「自分は特別だから学校に行かなくていい」
-
「失敗しても使命があるから大丈夫」
といった物語的な考えが強まると、現実的な問題解決能力が育ちません。
✔️ファンタジーを信じる過程で、子どもが親の期待に過剰に応える「過剰適応」や「親子の役割混乱」が起きる危険性
たとえば、
「あなたは天使だから守って」と保護者に言われると、
子どもは「守られる存在」でありながら、同時に「親を守る役割」や「親の期待を背負う存在」にもなってしまうのです。
このような状態では、子ども自身の気持ちを言葉にする機会が減り、「自分を自由に表現する力」 を育てることが難しくなります。
また、現実での失敗や不安を経験したときに、ファンタジーに逃げ込む習慣がつくと、
-
不登校
-
引きこもり
-
対人恐怖
-
抑うつ
-
自己肯定感の低下
といった二次的な問題が起きやすくなります。
これらが進むと、青年期以降に 「自分は社会で役に立たない」
「どうせ誰も自分を理解してくれない」 という強い孤立感が生まれ、
最終的には 社会参加や自立への大きな壁 になってしまいます。
子どもが「現実の中で生きる力」を少しずつ育てることは、とても大切です。
ファンタジーを完全に否定する必要はありませんが、
安全に現実に触れ、小さな挑戦を重ね、達成感を味わえる機会を支援すること が大切です。
そのためには、保護者のファンタジーに巻き込まれず、
冷静に子どもの発達課題と心理的安全を守る視点 が求められます。
10、最後に ─ 支援者の皆さんへ
支援が必要な保護者のファンタジーは、本人の心を守る 大切な防具 です。
しかし、それが強くなりすぎると、子どもの育ちを妨げる「鎧」となり、子どもが本来持つ力を閉じ込めてしまうこともあります。
支援者の役割は、その「防具」を無理に剥がすことではありません。
少しずつ現実の安全地帯を広げ、子どもと保護者が安心して歩める道を一緒に作っていく ことです。
福祉の皆さんは、誰よりも子どもと保護者に寄り添う、かけがえのない存在です。
保護者のファンタジーに巻き込まれず、でも決して見捨てず、一緒に現実に足をつける方法を模索する
その一つ一つの積み重ねが、やがて子どもの未来を守る大きな力になります。
どうか一人で抱え込まず、ぜひ職場にいる精神科医や児童精神科医、心理職、保健師などに気軽に相談してください。
「これは相談していいのかな?」と迷うテーマこそ、一緒に考える価値があります。
児童精神科医として、福祉司の皆様を心から応援しています。
11, 参考文献・資料
- 『臨床精神医学 第45巻 増刊号:妄想性障害』→精神科医専門医を目指す人向けの本です
- 『現代臨床精神医学 第12版』 →本格的な専門書です。
- 児童相談所ハンドブック(各自治体版)→いつも参考にしております。
- 『保護者支援の心理学』(ミネルヴァ書房)→名著です。繰り返し読んでいます。支援者の方にもおすすめです。