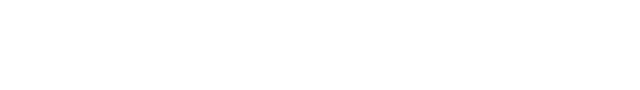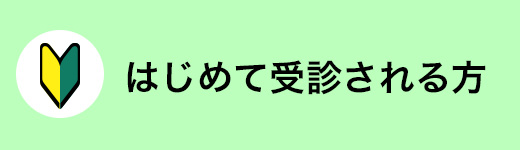子どもがリストカットをしていたら、親としてどう関わるべき?― 自傷行為はSOSのサイン
こんにちは。江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック、院長の三木敏功(児童精神科医、子どものこころ専門医)です
最近、「子どもの腕に切り傷を見つけた」「もしかしてリストカットでは…」というご相談を受けることが増えています。
親として驚き、動揺し、どう声をかけたらよいのか分からなくなるのは、当然のことだと思います。
今回は、子どもの自傷行為について、その背景や親としてできる関わり方、そして専門的な支援についてお話ししたいと思います。
※専門家向けの内容は→「先生だけには話すからね」― 子どもの“リストカット”に向き合う支援者のための9つの原則【児童精神科医が解説】
【目次】
- リストカットの現状 ―日本と海外の統計から
-
自傷行為とは? ― 「死にたい」ではなく「生きたい」のサイン
-
親がしてはいけない対応と、できる関わり方
-
自傷行為以外の対処法を一緒に見つけるために
-
脳科学・心理学から見る“自傷のしくみ”
-
一人で抱え込まず、専門家とつながってほしい
-
最後に ― あなたの寄り添いが、子どもを支える力になる
-
参考文献・書籍
1.リストカットの現状 ― 日本と海外の統計から見えること
リストカットなどの自傷行為は、思春期の子どもたちにとって決してまれな問題ではありません。日本国内でも海外でも、その発生率は年々増加傾向にあります。
■ 日本の統計
- 国立成育医療研究センターの「コロナ×こどもアンケート(第2回)」によると、
中学生の9.7%が「過去1年以内に自傷行為をした」と回答しています - 東京都教育委員会の2020年度調査では、都立高校生の24.6%が「自傷の経験がある」と答えています。
- 女子生徒の自傷率は男子の2〜3倍。特に中学2〜3年の女子に多い傾向が報告されています。
■ 海外の統計
- アメリカのCDC(疾病予防管理センター)による2021年の調査では、
高校生の17.2%が「過去12か月以内に意図的な自傷行為をした」と回答しています。
※女子では22.8%、男子では11.3% - カナダの公衆衛生庁(PHAC)の報告では、14〜17歳の青少年の約22%が「自傷行為の経験がある」とされています。
- イギリスでは、NHS(国民保健サービス)の調査によると、11〜16歳の青少年の18.8%が自傷行為を行った経験があると報告されています。
■ 傾向と共通点
世界中の調査で共通しているのは、
- 女子に多い(男子の2倍以上)
- 思春期に急増(中学〜高校)
- 自傷の理由は「死にたい」ではなく、
「感情のコントロール」「つらさから逃れたい」などが多いことです。
2,自傷行為とは? それは「生きるための手段」であることも
自傷行為とは、リストカットや皮膚を引っかくなど自分の体を意図的に傷つける行為です。
多くの方が「死にたいのでは?」と考えるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
特に思春期の子どもたちは、強いストレスや不安、怒り、寂しさ、自己否定の気持ちをうまく言葉にできず、自分を傷つけることで気持ちを一時的に落ち着けようとしていることがあります。
つまり、自傷は「死にたい」ではなく、「なんとか今を生きのびたい」「気持ちをどうにかしたい」というSOSのサインであることが多いのです。
3,親がしてはいけない対応と、できる関わり方
リストカットを見つけたとき、多くの親御さんが「なんでこんなことを?」「やめなさい」と責めたくなるものです。
しかし、否定されたと感じた子どもは、「どうせ誰にも分かってもらえない」と孤立感を深め、むしろ症状が悪化してしまうことがあります。
まずは驚きや戸惑いを抱えながらでも、子どもの気持ちを理解しようとする姿勢を持つことが大切です。
たとえば、こんな言葉が子どもとの距離を縮める手助けになるかもしれません。
-
「最近、何か無理してることや、辛いことがあったのかな?」
-
「びっくりしたけど、あなたのことがとても心配なんだ」
-
「困っていることがあれば、一緒に考えていけたら嬉しいな」
-
「一人で辛い想いをさせてごめんなさい。これからは、この辛い想いをお母さん(お父さん)と共有できたらいいな」
このように、「あなたの味方だよ」「大切に思っているよ」というメッセージを伝えることが、安心感や信頼感につながります。
また、「自傷をしている=その子がおかしい」というわけでも、「親の育て方のせい」というわけでもありません。
背景(原因)には、ストレス、学校や家庭、友人関係の悩み、発達特性、抑うつ、トラウマ体験による心の不調など、さまざまな要因が関わっていることがあります。
子ども達が背景(原因)を言葉で語られるようにサポートすることをいつも心がけてます。
4,自傷行為以外の対処法を一緒に見つけるために
自傷行為は、外から見ると「怖い」「理解しにくい」と感じられることが多いかもしれません。しかし、本人にとってはそれが「今、自分にできる精一杯の心の守り方」になっていることがあります。
特に子どもたちは、感情を言葉にして整理したり、人に助けを求めたりするスキルがまだ発展途上にあります。心に溜まった痛みや苦しみ、どうしようもない不安を自分の外に出す方法として、自傷という手段を選んでしまうことがあるのです。
自傷には「心を一時的に落ち着かせる効果」があることも
一部の子どもたちは、「自傷すると気持ちがスッとする」「頭の中が静かになる」と語ります。これは、痛みによって脳内に一時的な神経伝達物質(エンドロフィン・セロトニン)の変化が生じ、強い感情を抑える効果があるとされているからです。
しかし、これはあくまでも一時的な「対症療法」に過ぎません。しかも繰り返すうちに、その効果はだんだん薄れ(=効果の減弱が生じ)、より強い刺激を求めて自傷が深刻化する危険性があります。
つまり、“慣れ”が生じてしまうのです。
その結果、自傷行為が習慣化し、衝動的に行われるようになると、「やめたいのにやめられない」という新たな苦しみが生まれてしまいます。ですから、自傷の背景にある“感情の処理の難しさ”や“自分を保つ手段の少なさ”に気づき、そこに寄り添っていく必要があります。
一緒に「別の対処法」を見つけていくことが大切です
大切なのは、「自傷はダメ」「やめなさい」と一方的に否定することではありません。それよりも、「つらくなったとき、他にどんな方法があるかな?」と選択肢を一緒に探していく支援です。
たとえば、以下のような方法が自傷に代わる対処法として有効な場合があります:
- 手を冷たい水で洗う/氷を握る/ゴムを弾くなど、安全な身体刺激で衝動を逸らす
- 深呼吸やマインドフルネスを使って感情を落ち着ける
- 思いをノートに書き出す・絵で表現する
- 誰かに言葉で「今つらい」と伝える練習をする
- お気に入りの香りや音楽、落ち着くぬいぐるみなど五感に働きかけるものを使う
- ペットや植物に触れる/外に出て光を浴びる
もちろん、これらの方法がすぐにうまくいくとは限りません。自傷行為が強い「癖」になっている場合、本人の意志だけで切り替えるのは非常に難しいこともあります。ですから、無理に止めさせるのではなく、「少しずつ、他の方法も使えるようになろうね」と声をかけることが大切です。
当院の支援のあり方
当院では、現時点で心理師によるカウンセリングは実施していないため、主に薬物療法によるサポートが中心となります。ただし、心理的ケアの必要性が高いと判断される場合には、外部の心理師や医療機関をご紹介しております。
自傷への対応には、以下のような支援が組み合わさることが望ましいです:
|
支援の種類 |
具体例 |
|
生活面のケア |
睡眠・食事・活動のバランスを整える |
|
心理的支援 |
認知行動療法(CBT)、自尊感情を育てる療法、トラウマケアなど |
|
家庭支援 |
保護者の心理的サポート、関わり方の工夫 |
|
社会的支援 |
学校の支援体制、福祉機関との連携、居場所の確保 |
|
薬物療法 |
抑うつや不安、衝動性への対応(必要に応じて) |
支援の中心は「本人が安全に、希望を持って生きられる環境を整えていくこと」です。
それは医療だけでなく、家庭、学校、地域の関わりがそろって初めて成り立つものです。
5,脳科学・心理学から見る“自傷のしくみ”
自傷行為を理解するうえで、近年の脳科学や心理学の知見がとても役立ちます。
自傷は一見「なぜそんなことを…」と思える行動ですが、脳と心の働きを見ていくと、その裏にある仕組みが見えてきます。
■ セロトニン・エンドルフィンと「気持ちの安定」
脳内には「セロトニン」という物質があります。これは、心のバランスを保ち、不安や衝動性を抑える“安定剤”のような働きをします。
しかし強いストレス状態では、このセロトニンの働きが弱くなり、情緒が不安定になったり、感情のコントロールが難しくなったりします。
このようなとき、自傷行為が一時的に脳内の神経伝達物質(エンドルフィンやセロトニン)を増やす働きを持つことがあると指摘されています。つまり、「傷つけることで、逆にホッとする」という現象が起こるのです。
これは“甘え”や“かまってほしい”からではなく、脳の危機的な状態に対する自己防衛的な行動ともいえるのです。
■ 前頭前野と「衝動のブレーキ」
脳の前方にある「前頭前野」という部分は、“感情をコントロールする司令塔”の役割を担っています。
この部分は思春期以降にゆっくりと発達するため、小中学生や思春期初期の子どもは、怒りや不安などの感情を抑える力がまだ未成熟です。
特に、発達特性「ADHD(多動性衝動性注意欠陥症)やASD(自閉症スペクトラム症など」があるお子さんは、この前頭前野の働きに特徴があり、
-
「考えるより先に行動が出てしまう」
-
「一度浮かんだ考えを止められない」
といった傾向が強く現れます。
つまり、自傷は“理屈では止められない”行動であることも多く、本人の努力不足ではないという視点が重要です。
■ 心理学的視点:「感情調整の未発達」と「自分を責めるクセ」
心理学的には、自傷は「感情調整機能の未発達」と「過剰な自己否定」が重なったときに起こりやすいと考えられています。
たとえば、
-
小さいころから「我慢しすぎる」環境にいた
-
感情を外に出すことを責められてきた
-
自分の感情や欲求を表現することに罪悪感がある
…こうした背景を持つお子さんは、「つらい気持ちを感じたとき、どうしていいか分からない」という状態に陥りやすいのです。
その結果、「自分を傷つけることで感情を処理する」という方法しか選べなくなってしまう場合があります。
このように、自傷行為は単なる“行動の問題”ではなく、脳と心のしくみに根ざした現象です。
「注意してやめさせる」だけでは解決せず、専門的な視点でのアセスメントと関わりの再構築が求められます。
6,一人で抱え込まず、専門家とつながってほしい
子どもが自傷していると気づいたとき、親御さんは「自分が悪かったのでは」と自分を責めてしまうこともあります。
でも、親が一人で抱え込む必要はありません。
むしろ、早めに専門機関、支援者につなげることが、子どもを守ることにつながります。
相談先として
-
スクールカウンセラー,養護教諭等の学校
-
教育相談室
-
保健センター
-
児童相談所等の福祉機関
-
児童精神科のクリニックや病院 などがあげられます。
7,最後に
子どもの自傷行為は、親として非常に心配でつらい出来事です。
でも、その背景には、「助けてほしい」「分かってほしい」という切実な気持ちが必ず隠れています。
「自傷をやめさせる」のではなく、「自傷しなくても乗り越えられる力」を少しずつ育てていく。それが、私の目指す支援です。
たとえ時間がかかっても、本人が自分らしい方法で困難を乗り越えていけるようになることを信じ、寄り添い続けていきたいと考えています
焦らず、責めず、まずは子どもに寄り添いながら、必要な支援につなげていきましょう
8, 参考文献・書籍
1,National Institute for Health and Care Excellence (NICE)(2022)
Self-harm: assessment, management and preventing recurrence. NICE guideline [NG225]
→イギリスの公式ガイドライン。自傷行為の国際標準となる評価と支援モデル。大変読みやすく、勉強になりました。
2,American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP)(2001)
Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Suicidal Behavior
→自傷・自殺に対する包括的な臨床評価と治療方針を示す実践的ガイドライン。やや古いですが、参考にしています。
3,Klonsky, E. D.(2007)
The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence
Clinical Psychology Review, 27(2), 226–239.
→ 自傷行為が果たす心理的機能(感情調整、対人操作など)を理論的に整理した重要文献。必読論文かな。
4,松本俊彦(2012)
『自傷行為の理解と支援―なぜ若者は自分を傷つけるのか』
金剛出版
→若者の自傷行為に向き合う現場からの貴重な知見を収めた一冊。支援者必読本かなと思います。歴史的名著。
5,松本俊彦(2015)
『もしも「死にたい」と言われたら―自殺リスクの評価と対応』
中外医学社
→自傷と自殺の対応を具体的に示す、支援者のための実践的指針。支援者の必読本です。何度読んでいます。
6,岡田尊司(2011)
『アタッチメントと愛着障害』
NHK出版
→ 自傷行為と愛着形成の関係を心理学的に読み解く、理解を深める一冊。大変勉強になりました。