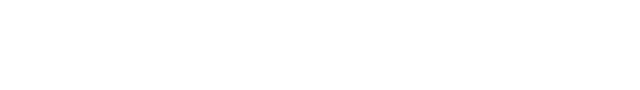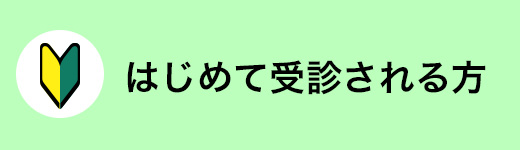発達障害のグレーゾーンってどういう意味?― 児童精神科医が解説します ―
こんにちは。
江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック、院長の三木敏功(児童精神科医 子どものこころ専門医)です。
今回は、保護者の方からよくご質問いただく「発達障害のグレーゾーン」という言葉について、児童精神科医の視点からわかりやすくお話ししたいと思います。
【目次】
-
「グレーゾーン」ってどういうこと?
-
グレーゾーンの子に見られる特徴
-
診断がつかない=問題ない?
-
なぜ診断がつかないことがあるのか
-
大切なのは「診断名」よりも「理解と支援」
-
早めの気づきと、無理のない対応が未来を変える
-
最後に:迷ったら、相談してください
1. 「グレーゾーン」ってどういうこと?
「発達障害のグレーゾーン」とは、正式な診断には至らないけれど、生活や人間関係の中で困りごとがある状態を指す、非公式な表現です。
たとえば…
-
家では大丈夫なのに、学校でトラブルが多い
-
発達検査では平均的だが、現実には困っている
-
環境や年齢によって困りごとがはっきりしてくる
こうした子どもたちは、「白(定型発達)」でも「黒(診断確定)」でもない、“中間のグレー”に位置づけられます。
2. グレーゾーンの子に見られる特徴
グレーゾーンのお子さんには、以下のような傾向が見られることがあります。
-
集団行動が苦手/こだわりが強い
-
注意力や集中力が続かない
-
気持ちの切り替えが難しく、癇癪を起こしやすい
-
友達との距離感が独特でトラブルになりやすい
-
自信がなく、失敗を極端に避けたがる
-
「なんとなく育てにくい」と感じられることが多い
こうした特徴が、本人の生活にどれくらい影響しているかによって、支援の必要性は異なります。
3. 診断がつかない=問題ない?
いいえ、それは大きな誤解です。
診断がつかないからといって、困りごとがないわけではありませんし、支援が不要という意味でもありません。
むしろグレーゾーンの子どもたちは…
-
制度の支援対象になりにくく
-
周囲から「努力不足」と誤解されやすく
-
自尊心を失いやすい
というリスクを抱えています。
このような状態を放っておくと、不登校、抑うつ、自傷などの二次的な問題につながることもあります。
4. なぜ診断がつかないことがあるのか
発達障害の診断には、「特性の有無」だけでなく「社会生活への影響の程度」も大きく関わります。
たとえば:
-
家では落ち着いていても、学校では困っている
-
年齢とともに困りごとが目立ってきたが、まだ軽度
-
検査では平均の数値だが、実生活では支障が出ている
こういったケースでは、診断が見送られることがあります。
しかし、「診断がつかない=支援が不要」では決してありません。
5. 大切なのは「診断名」よりも「理解と支援」
私たちが最も大切にしているのは、「発達障害かどうか」ではなく…
-
どんな特性があるのか?
-
どの場面で困りごとが出やすいのか?
-
どんな支援や工夫が合っているのか?
といった“見立て”と“関わりの工夫”です。
診断名はあくまで支援につなげるための道具であり、目的そのものではありません。
6. 早めの気づきと、無理のない対応が未来を変える
グレーゾーンの子どもたちでも、周囲の理解と工夫があれば、大きく変わっていける力を持っています。
たとえば、こんな支援が有効です:
-
認知特性に合った学習支援(見える化・ステップ分けなど)
-
予定変更に弱い子への“予告”と“見通し”の提示
-
小さな成功体験を積ませて、自信を育てる関わり
-
感覚過敏への配慮(音・光・衣類などの刺激)
-
視覚的にわかりやすい家庭内ルールの提示(カードや色分け)
-
感情コントロールを学ぶ支援(気持ちの温度計・怒りメーターなど)
こうした支援は、診断の有無にかかわらず、“その子らしく過ごせる環境”を整えるうえでとても有効です。
7. 最後に:迷ったら、専門家・専門機関に相談してください
「うちの子、グレーゾーンかもしれない…」
そう感じた時点で、すでに第一歩を踏み出していると言えます。不安を抱えながらも、子どもの特性に目を向け、必要な支援を考える姿勢こそが、子どもたちにとって最大の力になります。
グレーゾーンは、「問題が軽い」わけではありません。
気づかれにくく、理解されにくいからこそ、本人とご家族が孤立しがちです。
そして、相談先としては発達支援センター、学校のスクールカウンセラー、教育相談室、療育機関、保健所、児童相談所、小児科・児童精神科の医療機関などがあげられます。
お子さんの特性を理解し、その子らしい未来へつなぐお手伝いができたらと思います。
8. 【参考文献・出典】
-
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
※発達障害の国際的診断基準。グレーゾーンの判断における「機能障害の程度」の記述が鍵になります。精神科医は必読本であります。いつもカバンに持ち歩いています -
Lai, M. C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2014). "Autism." The Lancet, 383(9920), 896–910.
※ASDの神経科学的理解とスペクトラム概念について、国際的に引用される論文。有名な論文であります。 -
Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2018). "Autism spectrum disorder." Nature Reviews Disease Primers, 4, 5.
※ASDの診断・支援・予後について包括的にまとめた総説。日本の文化・事情とそぐわない部分もありますが、とても勉強になります -
梅永雄二(2022)『発達障害のある子の理解と支援』中央法規出版
※日本の教育・心理・福祉実践に即した事例・支援法の体系的な解説。何度も読んでいます。 -
日本児童青年精神医学会 編(2021)『児童青年精神医学テキスト』金剛出版
※児童精神科医が診断と支援を考える際のスタンダードな教科書です。多くの児童精神科医は持っている印象です。