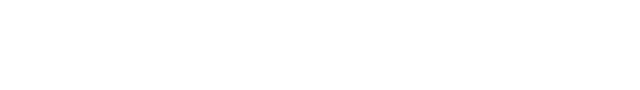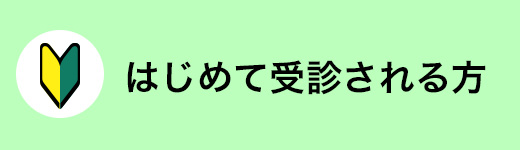【児童精神科医が解説】発達障害(ADHD・ASD)の診断名はいつ伝える?年齢別の伝え方と注意点
こんにちは。
江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック 院長の三木敏功(児童精神科医 子どものこころ専門医)です。
診療の現場で保護者や支援者の方からよくいただくご相談のひとつに、
「この子に診断名って伝えたほうがいいのでしょうか?」
「いつ、どんなふうに話したらいいのでしょうか?」
という悩みがあります。
お子さんの発達の遅れや心の不調について、病院で名前がついたとき、、、
たとえば「ADHD」「自閉スペクトラム症」「不安障害」などの診断名は、支援者、保護者にとってもこども本人にとっても、大きな意味を持ちます。
今回は、児童精神科医の立場から
「診断名をこどもにいつ、どのように伝えるべきか」
その考え方やポイント、注意点を、できるだけわかりやすく解説します。
【目次】
- なぜ診断名を伝えるかどうかで悩むのか?
- 診断名には“力”がある
- 告知を検討するきっかけとなる3つの場面
- 年齢と発達段階による伝え方の違い
- 診断名を「ラベル」にしないために
- 保護者が気をつけたい3つの視点
- 告知のあとに大切な“見守り”と“言葉がけ”
- 周囲の大人とどう共有するか?診断名の扱い方
- 「診断名=人生」ではない。これからを一緒に考えるために
- まとめ:告知はスタートライン
- おすすめの書籍
1. なぜ診断名を伝えるかどうかで悩むのか?
保護者の方が診断名の「告知」に戸惑うのは、とても自然なことです。
なぜなら、
- こどもが傷つかないか
- その診断名で自分を決めつけてしまわないか
- 学校や友人関係に影響が出ないか
といった不安が一気に押し寄せるからです。
「この子に障害があるなんて言いたくない」
「一度伝えてしまったら取り返しがつかないのでは」
といった親心から、悩みを深める方も多くいらっしゃいます。
2. 診断名には“力”がある
診断名というのは、一種の“ことばの力”を持っています。
その子の特性や困りごとに名前をつけることで、次のようなことが可能になります。
- 専門的な支援につながる
- 支援者との共通言語になる
- 「自分のせいではなかった」と理解できる
一方で、こどもがまだ十分に自分を言葉で捉えられていないとき、
診断名だけが一人歩きして「私は発達障害だからダメなんだ」と思い込んでしまう危険性もあります。
つまり、診断を告知することは
伝え方を間違えれば、病状悪化に繋がりかねないので、慎重に扱うべき情報なのです。
3. 告知を検討するきっかけとなる3つの場面
診断名の告知に“正解のタイミング”はありませんが、以下のようなタイミングでは前向きに検討されることが多いです。
① 本人が「なぜ通院しているの?」「自分のことをしりたい」と聞いてきたとき
→ 成長とともに自然と湧いてくる疑問です。「風邪でもないのに、どうして病院?」と感じ始めたら、ある程度説明する必要があります。
② 自身の内面を客観視でき、「自分は変だ」「自分は普通じゃない」と思い始めたとき
→ 自分を責めるより、「特性があるから困りごとが起きやすい」という視点をもつことが救いになります。
③ 二次障害(うつ、不登校、自己否定など)が出てきたとき
→ 診断名の理解は、自分の内面との距離をとり、冷静に自分を見つめる手助けになります。
4. 年齢と発達段階による伝え方の違い
こどもに診断名を告げるときは、言葉選びとタイミングが非常に大切です。以下はあくまで一例ですが、参考になる目安です。
■ 幼児〜小学校低学年(5~8歳)
- 正式な診断名は用いず、「好きなことには没頭するという過集中の特徴あるよね。」「マイペースで自分の意見を言える信念の強いタイプだね」など、やわらかい言葉で説明。
- 自己肯定感を傷つけないよう、ポジティブな特性とセットで話す。
例:
「○○くんは、色んなことに気づけるアンテナがあるんだよ。そのぶん、少し疲れやすいだけなんだよ」
■ 小学校高学年(9~12歳)
- 言葉の理解力が高まってくるため、診断名の説明を少しずつ始める時期。
- ネガティブなイメージを避け、特性と対処のコツを中心に伝える。
例:
「あなたには“ADHD”というタイプの傾向があるけど、それは“集中しにくいけど、ひらめきがすごい”ってことでもあるんだよ」
■ 中学生~高校生
思春期のこどもに診断名を伝えるとき、幼少期と比べて「本人の自己認識の強さ」と「他者からの評価への敏感さ」が格段に増している点を意識する必要があります。
1. 思春期特有の心理をふまえた配慮
- 「普通じゃない」と言われたように感じる:診断名=異常と誤解されやすく、「どうせ自分は変だから」と思い込むリスクがあります。
- 自己否定が強まる時期:診断名が「欠点の証明」のように受け取られると、自己肯定感の低下を招くことも。
- 「他人に知られたくない」気持ち:自分の弱みを人に知られることに強い不安を感じやすいため、説明の際はプライバシーに十分配慮します。
2. 伝えるときのステップとポイント
ステップ①
こどもの気持ちを確認する
いきなり診断名を告げるのではなく、まずは本人の中にある疑問や不安を言葉にしてもらうことが重要です。
例:「最近、自分のことどう思ってる?」「中学生(高校生)になって、何か困っていることある?」
この対話の中から、「自分は他の人と違うのでは」「集中できないのは自分だけ?」といった違和感や悩みを本人が感じている場合には、診断名の説明をする土台ができていると判断できます。
ステップ②
診断名を伝え、「特性と強みの話」につなげる
例:「◯◯さんには『ADHD(注意欠如・多動症)』という診断がつくかな」
「これは、集中が難しいことや、じっとしているのが苦手な傾向がある“タイプ”のこと。欠点じゃなくて、脳の特徴なんだよ。」
「実は、ADHDの人には“アイデアが豊富”“切り替えが早い”“エネルギーがある”という強みもある。困ることもあるけど、それを知っておけば対応しやすくなる。」
このように、「弱み」ではなく「特性」として説明し、同時にポジティブな側面を示すことで、自己理解と安心感を育みます。
ステップ③
本人のペースに合わせて「情報の量」を調整する
中高生になると、自分でネット検索する力もあるため、本人が独自に診断について調べる可能性があります。
そのため、伝える側が主導権をもちながらも、こどもが安心して質問できる関係性をつくることが重要です。
「ネットにはいろんなことが書いてあるけど、信頼できる情報は一緒に探そう」
「何か読んで気になったことがあれば、いつでも聞いてね」
こうした「対話の継続性」が、こどもが誤情報に振り回されず、診断を前向きに受け止める力につながります。
3. 第三者と一緒に伝えることがとても大切
診断ができるのは、医師のみとされています。保護者や学校の先生、心理師が単独で診断の告知を担うことは、望ましいとは言えません。
よって、ご本人と保護者以外に医師が告知に参加することで、本人が客観的に自分を見つめやすくなり、受け入れやすくなります。その告知後の本人へのフォローもしやすくなります。
4. よくある質問・不安への返し方(想定Q&A)
|
こどもの質問・反応 |
返答例 |
|
「これって一生治らないの?」 |
「脳の特徴だから“完全になくなる”わけではないけど、工夫すれば困らなくなることがたくさんあるよ」 |
|
「友達にバレたらどうしよう」 |
「伝える・伝えないは自分で決めていいこと。誰に話すかは大人も一緒に考えるね」 |
|
「なんで自分だけこんな目にあうの?」 |
「これは“悪いこと”じゃなく、“君のタイプ”だよ。それを知ることで、強みに変えていくことができるんだ」 |
5. 書籍などのサポートツールの活用
- 本人の理解を助けるために、診断名をテーマにした読みやすい本や動画を一緒に見ることもおすすめです。
例:
『発達障害がよくわかる本』(健康ライブラリー シリーズ) 監修:本田秀夫
→発達障害(ASD、ADHDなど)の定義・分類・対応法・生活や学校での関わり方を、入門者向けにわかりやすく解説した一冊です
まとめ:思春期の診断名告知のキーワード
- 「対話」>「一方的な説明」
- 「タイプ」「特徴」>「障害」「病気」
- 「強み」も必ずセットで伝える
- 「1回で完了」ではなく「段階的に理解を育む」
- 信頼できる大人との「安心できる対話環境」づくりが最優先
5. 診断名を「ラベル」にしないために
診断名を伝えるときに、もっとも注意しなければいけないのが
「診断名=自分そのもの」になってしまうリスクです。
たとえば、
- 「どうせ自分は発達障害だから…」
- 「うつ病だから努力しても無理なんだ」
- 「病気だから嫌われるんだ」
といった思い込みは、本人の成長や挑戦を妨げます。
私たち専門家がよく伝えるのは、
診断名は「ラベル」ではなく「取扱説明書」や「地図」になるものです。
つまり、「診断名の告知=支援」
その子の“可能性を広げるためのヒント”と捉えていただきたいのです。
例:
「ADHDを先生から教えてもらって良かった。過去は、色々失敗してきた理由が凄いよくわかった。もっと自身のADHDの特徴を皆と一緒に学んでいきたい」
6. 保護者が気をつけたい3つの視点
① 自分の気持ちを整理しておく
親が不安や罪悪感を強く抱いたまま告知すると、その感情が子どもに伝わってしまいます。まずは自分が「この子の理解が深まるチャンスなんだ」と気持ちを整理することが大切です。
② 比較・決めつけをしない
「○○ちゃんは普通なのに、うちの子は…」
「あなたはADHDなんだからこうしなさい!」
といった言い方は、自信を奪う原因になります。
③ 言いっぱなしにしない
告知は一度きりの“伝達”ではありません。繰り返し、丁寧に話し、気持ちの変化を見守る“対話”が何より大切です。
7. 告知のあとに大切な“見守り”と“言葉がけ”
診断名を伝えたあと、こどもがどう感じたかを気にかけることがとても重要です。
- 「びっくりした?」
- 「何か不安に思ってることある?」
- 「他に知りたいことある?」
など、対話の機会を定期的に持ちましょう。
特に、告知後数日は気持ちが不安定になることもあります。
「いつもどおり」で接しながら、変化に気づいたらそっと寄り添ってください。
8. 周囲の大人とどう共有するか?診断名の扱い方
診断名は、学校や支援機関など他の大人にどう伝えるかも重要なテーマです。
- 学校の担任やスクールカウンセラーには、本人・保護者の同意を得たうえで共有することが多いです。
- 放課後デイサービスや福祉サービスの利用には診断書が必要になる場合もあります。
- 伝える際は、「診断名」だけでなく「どんな支援が有効か」まで共有できるとより効果的です。
9. 「診断名=人生」ではない。これからを一緒に考えるために
診断名がついたからといって、将来が決まるわけではありません。
むしろ、そこから「どう生きていくか」「どんな支援を選ぶか」を一緒に考えていくことこそが重要です。
診断名は、「あなたらしさを見つけるきっかけ」であり、
「あなたに合った道を探すためのツール」です。
10. まとめ:告知はスタートライン
診断名を伝えることはゴールではなく、「理解と支援の始まり」です。
- 無理に伝える必要はありません
- でも、伝えることで「自分を知る力」が育つこともあります
- 最も大切なのは、診断名を「意味あるもの」にできるよう、支える大人が一緒に考えていくことです
こどもには、自身の診断を聞く権利はあります。
「診断告知=支援」になるように、
子どもに「診断名を聞いて良かった」と思ってもらえるように様々な工夫や準備をしていきましょう!
11.【推薦図書】
- 村瀬嘉代子『子どもに診断名をどう伝えるか』ミネルヴァ書房→何度も何度も読んでいます。とても参考になります。
- 中井久夫『子どもの心を読む』みすず書房
- 山登敬之『「発達障害」と間違われる子どもたち』講談社現代新
- 本田秀夫『発達障害の子どもを理解するために』中央法規出版