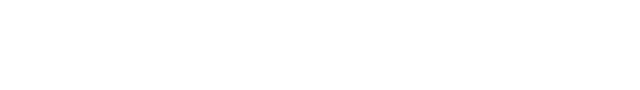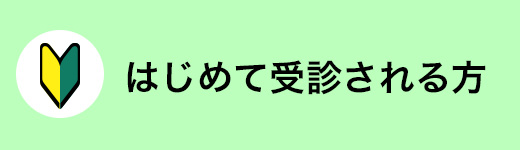癇癪(かんしゃく)に対する薬物療法という選択肢-辛さが減り、成長するきっかけのために-
こんにちは、江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック院長の三木敏功(児童精神科医)です。
今回は、多くの保護者の方からご相談いただく「癇癪(かんしゃく)」についてお話をさせていただきます。
癇癪とは、自分の思い通りにならない時や嫌なことがあったときに、怒りやイライラを抑えられず、激しく泣いたり怒ったり、物を投げたりしてしまう状態を指します。時には自分や他人を傷つけるような行動にまで発展してしまうこともあり、保護者の方にとってとても大きな悩みのひとつです。
■ 年齢ごとの癇癪の特徴
乳幼児期(2〜3歳)
この時期の癇癪は、発達段階においてよく見られる自然なものです。言葉でうまく気持ちを伝えられないことから、感情を爆発させてしまうのは珍しくありません。多くの場合、成長とともに少しずつ落ち着いてきます。
幼児〜学童期(4〜7歳)
この頃になると、自分の気持ちを少しずつ言葉で表現できるようになってきます。にもかかわらず、癇癪が頻繁に起こったり、激しさが強まったりする場合は注意が必要です。年齢とともに感情のコントロールがついてくるのが一般的ですが、極端な癇癪が続くようなら、支援を検討しても良いタイミングかもしれません。
小学校高学年~思春期以降
中学生や高校生になっても癇癪が続く場合、本人も強い苦しさを抱えていることが多く見受けられます。また、学校生活や家庭内での関係にも大きな影響が出ているケースが多いため、早めの相談が望まれます。
■ こんな時は支援機関へ相談を
以下のような様子が見られたときは、専門機関への相談をおすすめします。
- 癇癪が長時間続く(30分以上)
- 癇癪の頻度が非常に高い(週に何度もある)
- 物を壊したり、自分や他人を傷つけたりする行動がある
- 癇癪のあとに本人が強い落ち込みや自信の喪失を見せる
- 学校や園で指摘されている
- 保護者自身がストレスで育児が辛くなっている
相談先としては、以下のような支援機関があります。
- 発達支援センター
- 療育機関
- 園や学校のスクールカウンセラー
- 児童相談所
- 保健所や子育て支援センター
- 小児科や児童精神科などの医療機関
■ 癇癪に対するサポート・治療について
まず薬を使わずに癇癪を改善できるような支援を提案させて頂いております。療育や心理カウンセリング等でお子さん自身が感情を上手にコントロールする力を育てることや、ご家庭・学校での関わり方を調整することから始めます。環境や対応の工夫だけで落ち着く場合もありますので、その可能性を最初に探ります。
(大変お恥ずかしい話ですが、現時点では、当院では、心理カウンセリングや療育の支援は実施しておりません)
しかし、さまざまな工夫をしても改善が見られない場合、医師しかできない支援のひとつとして、心の薬を使うことも選択肢となります。
■ 薬物療法についての考え方
「子どもに薬を飲ませるのは不安」「できれば薬を使いたくない」といった保護者の方の気持ちは、よく理解しています。そうした不安に寄り添いながら、当院では薬の使用についても、必要最低限・短期間を原則とし、慎重に判断しています。
お薬を使うことで、怒りの爆発がやわらぎ、周囲の働きかけが届きやすくなることがあります。そうして感情をコントロールする練習を積み重ねていけるよう、薬は「問題の先送り」ではなく「成長へのサポート」として位置づけています。
薬の使用中は、定期的に副作用や効果のチェックを行い、安心して継続できるようサポートいたします。状態が安定してきたら、徐々に減薬・中止することも可能です。
■ 最後に
毎日のお子さんの癇癪に悩まされ、家族みんなが疲れきってしまう…。そんな時は、一人で抱え込まず、どうか専門機関にご相談ください
当院では、保護者の皆さまと一緒に、お子さんが穏やかで安定した毎日を過ごせるよう、最善の方法を考えてまいります。