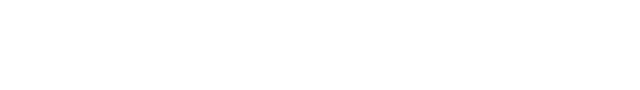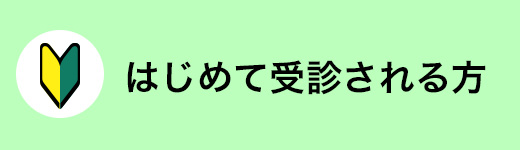表面的に“いい子”すぎる、あの子が心配なときに ― その子のSOSをどう見抜く?児童精神科医が解説します
こんにちは。
江戸川篠崎こどもと大人のメンタルクリニック、院長の三木敏功(児童精神科医・子どものこころ専門医)です。
今回は、「“いい子”であろうとする子どもたちの本当の気持ち」について、脳科学と心理学の視点から詳しく解説したいと思います。
1. “いい子”は本当に「困っていない子」なのか?
子育てや教育現場で、「この子は手がかからない」「いつもニコニコしている」「とってもいい子です」と言われる子どもがいます。もちろん、落ち着いていて周囲に配慮できることは素晴らしいことです。
しかし、児童精神科医は時に、「いい子」がむしろ“心の危機を抱えているサイン”かもしれないという視点を持って診療しています。
2. “いい子”の裏側にある感情とは?
子どもが「いい子」でいようとする理由は、多くの場合、こうした不安や恐れです:
- 「怒られたくない」
- 「嫌われたくない」
- 「迷惑をかけたくない」
- 「親や先生に心配かけたくない」
- 「自分の気持ちより、周りを優先しなきゃ」
これは、誰かから強制されたというより、子どもが“自分なりに空気を読んで”学習した行動です。
3. 【脳科学から見る】“過度にいい子すぎる”の脳は緊張状態にあるかも
最新の脳科学では、慢性的なストレス環境に置かれた子どもは、扁桃体(感情の中枢)が過活動となり、警戒状態が持続しやすくなることがわかっています。
その結果、次のような反応が起きます:
- 表面は笑顔でも、脳は「安全でない」と判断している
- 前頭前野(自己調整・意思決定の部位)が疲弊しやすくなる
- 自律神経が乱れ、頭痛・腹痛・睡眠障害・過呼吸などの身体症状が出る
つまり、“いい子”の中には、「いい子を演じることが脳にとっても負担」になっている子がいるのです。
4. 【心理学から見る】自我状態理論で読み解く“いい子”
交流分析(Transactional Analysis:TA)では、人の心の状態を以下の3つの自我状態に分類します。
|
自我状態 |
内容 |
子どもの行動例 |
|
親の自我(P) |
ルール・道徳・価値観 |
先生や親の期待を優先する、自分に厳しい |
|
大人の自我(A) |
論理的・現実的 |
我慢をして空気を読む、感情を抑える |
|
子どもの自我(C) |
感情・欲求・創造性 |
甘えたい、泣きたい、自由に振る舞いたい |
“いい子”は、多くの場合、「親の自我(P)」と「大人の自我(A)」が強く働き、「子どもの自我(C)」が抑え込まれている状態です。
本来、子どもにとって大切な「泣きたい」「怒りたい」「遊びたい」という感情が、表に出せずに“演じる”形になってしまいます。
この抑圧が長期化すると、自我のバランスが崩れ、心身の不調や極端な行動に表れることがあります。
5. よくある“いい子”のサイン
以下のような子どもの様子が見られたら、「心のSOSかもしれない」と一度立ち止まって考えてみてください。
- 頑張りすぎているのに「大丈夫」と言い続ける
- 親や先生の前ではニコニコ、家で突然泣き出す
- 本音を言わず、「言われた通りにする」ことを選ぶ
- 小さな失敗でも激しく自己否定する
- 理由不明の体調不良が続く(頭痛、腹痛など)
6. 保護者・支援者にできる5つの関わり方
(1)「いつもありがとう。がんばりすぎてない?」と声をかける
→ 子どもが“気づいてもらえた”と感じることが大切です。
(2)「泣いてもいい」「失敗しても大丈夫」と繰り返し伝える
→ 子どもの“子どもの自我(C)”を安全に解放できるよう促します。
(3)「怒らないから教えてね」と安心をつくる
→ 自分の本音や弱さを打ち明ける“予告”が必要です。
(4)何かしてくれたら「ありがとう」、しなくても「好きだよ」
→ 条件付きの愛情ではなく、無条件の承認を。
(5)「あなたらしくていいね」を増やす
→ 他人基準ではなく、「自分らしさ」を肯定する機会をつくりましょう。
7. 子どもに必要なのは「安心して失敗できる場所」
“いい子”という仮面の下で、子どもは必死に「安全」を求めています。
でも本当に必要なのは、「がんばらない自分でも受け入れてくれる場所」です。
泣いたり、甘えたり、失敗したり。
そんな子どもの姿を、「だらしない」と思わず、「ここにいていいよ」と伝えてあげてください。
8,最後に:まとめ
“いい子”を演じる子どもたちは、実は心も脳も常に緊張した状態にあります。
一見、問題なく見えるかもしれませんが、内側では「本当の自分」を押し殺して、周囲に合わせようとがんばり続けています。
心理学の「自我状態理論」では、このような状態を、子どもらしい感情や欲求を表す“子どもの自我(C)”が抑えられた状態と考えます。本音を言えず、ただ「期待に応える自分」を演じ続けてしまうのです。
こうした子どもに必要なのは、「もっと頑張れ」や「えらいね」といった“評価”ではありません。
ありのままの自分でいても大丈夫なんだという、安心感と無条件の受容こそが、心を回復させる力になります。
「失敗してもいいよ」「泣いてもいいんだよ」
そんな言葉や態度が、子どもにとっては心の安全基地となり、本当の意味での自己肯定感や感情の安定を育ててくれると私は信じています。
9,関連図書
- 佐々木正美『子どもへのまなざし』(福音館書店)→保護者の方にも読みやすい本です。
- 明橋大二『子育てハッピーアドバイス』(1万年堂出版)→ 子育てハッピーアドバイスシリーズは全ておすすめです。
- 友田明美『子どもの脳を傷つけないために』(NHK出版)→ストレス・虐待と脳についてわかりやすく記されています。
- アン・スーザン・ウィットニー『“いい子”症候群の子どもたち』(大月書店)→何度も読んでいます。名著です。
- 岡田尊司『愛着障害 子ども時代を引きずる人々』(光文社)→岡田先生の本はとても読みやすく、おすすめです。
- エリック・バーン『自我状態と交流分析の理論』(TA理論解説書)→心理学の専門書です。